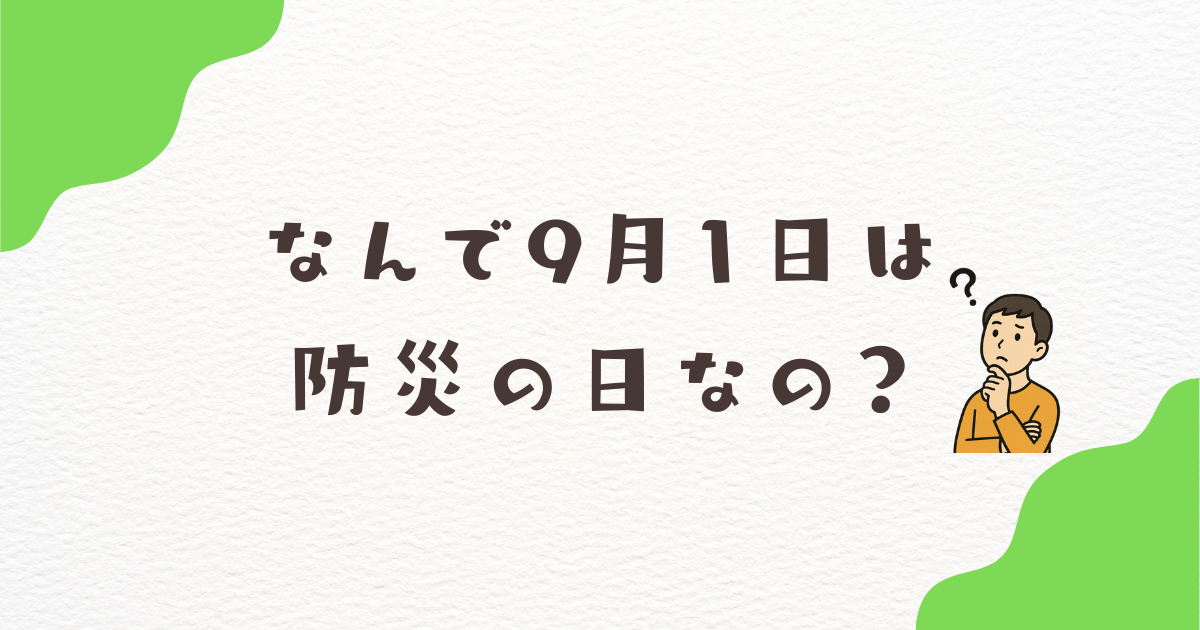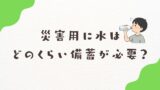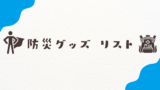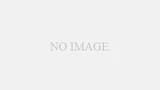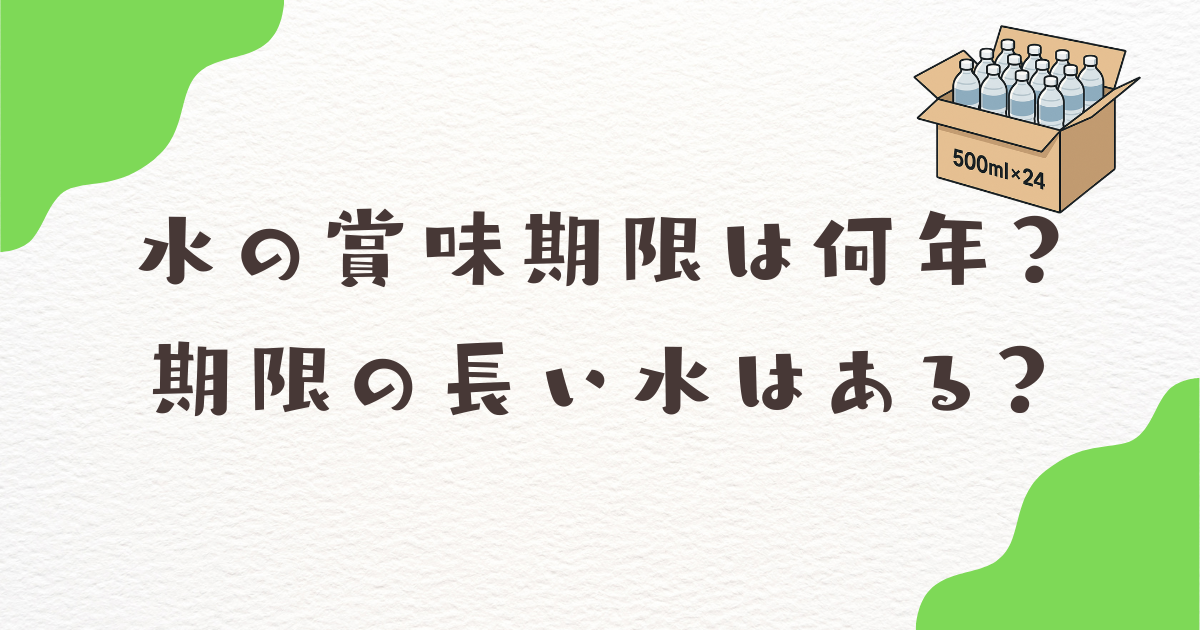9月1日「防災の日」とは
「防災の日」とは何か: 毎年9月1日は、日本で防災啓発のために定められた「防災の日」です。
政府・自治体など防災関係機関だけでなく、広く国民一人ひとりが台風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波など様々な災害への認識を深め、防災への備えを充実・強化することで、災害の未然防止と被害軽減に資することを目的としています。
いわば防災意識を高めるための記念日であり、全国で防災訓練や啓発イベントが行われます。
防災週間: また毎年、9月1日を含む1週間(8月30日〜9月5日)が「防災週間」に定められており、この期間に防災知識普及の講演会・展示会、防災訓練、防災功労者の表彰などが全国的に実施されます。
これは1982年に創設された仕組みで、1983年以降、この週が正式に防災週間として定着しました。
なぜ9月1日が防災の日なの?
9月1日という日付が選ばれた最大の理由は、1923年9月1日に関東大震災が発生した日だからです。
関東大震災は東京・横浜を中心に壊滅的被害をもたらし、死者・行方不明者が10万5千人以上にも及ぶ未曾有の大災害でした。
この大震災の記憶を風化させず、教訓を未来に活かすために、同日を「防災の日」と定めています。
さらに9月初頭は例年台風が多い季節でもあります。
暦の上で立春から数えて210日目にあたる「二百十日」がちょうど9月1日前後で、昔から台風が襲来しやすい厄日と警戒されてきました。
実際、1959年9月26日に伊勢湾台風が戦後最大級の被害(家屋流失・全半壊約15万戸、死者4,700人ほか)を出したことが契機となり、防災の日の創設につながりました。
稲の開花期にあたるこの時期に台風が来ると農作物に大打撃となるため、農村暦でも注意喚起の日とされてきたのです。
このような知識も踏まえ、9月1日は統計的根拠というより象徴的な意味で「防災の日」とされているのです。「災害への備えを怠らないように」という台風期への戒めの意味も込められています。
誰が防災の日と決めたの?
「防災の日」は、昭和35年(1960年)6月11日の閣議で「毎年9月1日を防災の日とする」ことが決定されたのが始まりです。
つまり国の決定として1960年に制定され、同年9月1日から初めて「防災の日」が実施されました。
決定に至った背景には前述の伊勢湾台風(1959年)の被害が大きく影響しており、「地震や風水害等に対する心構えを育成するため」に設けられたと公式に説明されています。
その後、昭和57年(1982年)5月11日の閣議決定により、一度1960年の閣議決定を廃止した上で改めて「防災の日」および「防災週間」を制定し直す措置が取られました。
これにより制度の整理が図られ、防災週間の概念が正式に加わります。
さらに翌昭和58年(1983年)5月24日には中央防災会議の決定で、毎年8月30日〜9月5日を防災週間とすることが定められ、現在の枠組みが確立しました。
要するに、1960年に防災の日が生まれ、1980年代に防災週間に発展しました。
制定の目的は「防災啓蒙」
防災意識の向上: 防災の日が制定された趣旨は一貫して「国民の防災意識を啓発し、防災対策を促進する」ことにあります。
1960年の官報にも「政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民一人ひとりが台風、高潮、津波、地震などの災害について認識を深め、これに対処する心構えを準備しようというのが『防災の日』創設のねらいである」と記されており、日頃からの備えと防災行動を皆で考え実践するきっかけとすることが目的と説明されています。
「もちろん、災害に対しては常日ごろから注意を怠らず万全の準備を整えていなければならない」が、それでも年に一度、防災について各人が家庭や職場で考え行動する日を設けよう――そうした理念で制定されたのが防災の日です。
この理念は現在も受け継がれており、9月1日は「防災意識を今一度改める節目の日」として位置づけられています。
年表で見る:防災の日の歴史
| 日付 | 出来事 | 概要/ポイント |
|---|---|---|
| 1923年9月1日 | 関東大震災(大正関東地震) | 11時58分、相模湾北部を震源とするM7.9。東京市・横浜市中心に壊滅、都市大火発生。死者・行方不明 約10万5千人、全壊11万棟、焼失21万棟。防災・都市計画見直しの契機に。 |
| 1959年9月26日 | 伊勢湾台風 | 戦後最悪の台風災害。高潮と暴風雨で甚大被害(死者4,697人・行方不明401人、負傷約3万9千人、全半壊・流出15万戸超、浸水36万戸超)。防災の日創設の直接のきっかけ。 |
| 1960年6月11日 | 「防災の日」制定(閣議了解) | 「毎年9月1日を防災の日」と正式決定(6月17日官報公示)。選定理由:関東大震災の教訓継承+台風期の厄日(二百十日)。以後、9/1の訓練・啓発が各地で開始。慰霊中心から訓練の日へ。 |
| 1982年5月11日 | 「防災の日・防災週間」再整理(閣議了解) | 「毎年9月1日=防災の日」「この日を含む1週間=防災週間」を明文化。功労者表彰等の全国的実施を規定。1960年の閣議了解は廃止し新枠組みに移行。 |
| 1983年5月24日 | 防災週間の期間を固定化(中央防災会議) | 期間を毎年「8月30日〜9月5日」に決定。統一運用と広報・訓練の集中実施をねらい。背景に1982年創設の防災功労者表彰の年次行事化など。 |
防災の日・防災週間の主な取り組み
9月1日の防災の日およびその前後の防災週間には、国や自治体、企業、学校、地域コミュニティなどあらゆるレベルで防災に関する行事が行われます。
ここでは代表的な取り組みを紹介します。
全国・自治体の防災訓練。
大規模な防災訓練: 防災の日には毎年、国主導の大規模な総合防災訓練が実施されます。
いちばん有名なものは、首相官邸主導の中央防災訓練で、首相以下全閣僚や関係機関が参加し、大地震や津波を想定した政府の初動対応訓練が行われます。
例えば令和4年9月1日の訓練では、岸田首相らが参加し和歌山県南方沖を震源とする地震を想定した訓練が行われました。
首都圏では「九都県市合同防災訓練」と称して、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県など9つの都県市が持ち回りで幹事となり、防災の日または防災週間中の適切な日に大規模訓練を合同実施します。
これは1979年から続く伝統的な訓練で、地域間の連携強化や相互応援の手順確認を目的としています。各年の幹事自治体に主会場を設け、住民参加型の救出・救護訓練や、陸海空自衛隊・消防・警察・医療機関など多数の機関が参加する総合訓練が展開されます。
例えば令和7年度(2025年)は埼玉県幸手市で中央会場訓練が計画されています。
これ以外にも全ての都道府県・市町村レベルで総合防災訓練が行われるのが通例です。各自治体は地域の想定される災害(首都直下地震、南海トラフ地震、水害など)に合わせて、住民参加の避難訓練や、消防・警察・防災関係機関との合同訓練を実施します。
たとえば南海トラフ巨大地震の想定地域では地震後の対応を一連で訓練したり、津波避難訓練を沿岸部で実施したりしています。
このように9月1日を中心に全国各地で防災訓練が行われ、人々が「もしも」の時の行動手順を確認する機会となっています。
慰霊・追悼行事
9月1日は関東大震災の忌日であることから、各地で追悼式や慰霊法要も執り行われます。
特に東京墨田区の横網町公園内にある「東京都慰霊堂」では、毎年9月1日に関東大震災犠牲者の慰霊大法要が営まれています。
東京都慰霊堂(旧震災記念堂)は震災で亡くなった約5万8千柱の遺骨を納めるために建設された霊堂で、昭和5年に完成して以来追悼の中心となってきました。
東京以外でも、大きな震災・災害を経験した地域では9月1日前後に慰霊祭が行われます。
横浜市や神奈川県では関東大震災の県内犠牲者慰霊式典、名古屋市では伊勢湾台風殉難者の慰霊式などが開催される例があります。
企業・学校での避難訓練
多くの民間企業でも、自社ビルでの従業員の避難訓練や初期消火訓練、安否確認システムのテストなどを9月1日に合わせて実施しています。
特に大規模ビルを所有する企業には年1回以上の防災訓練実施が法令で義務付けられており、「防災の日」はそれを遂行する良いタイミングとなっています。
小中学校や高校でも、この時期に避難訓練を行うところが多くあります。
9月1日がちょうど新学期開始直後に当たるため、防災の日に合わせて地震や火災を想定した全校避難訓練を行うのが恒例です。児童生徒たちは先生の指示で速やかに校庭など安全な場所へ避難する練習をし、避難後に点呼・安全確認をします。
学校によっては地域の消防署と連携して消火器の使い方講習を受けたり、防災授業として震災の歴史を学ぶ時間を設けたりもしています。
地域の防災イベント・体験会
防災週間中には、自治体や消防機関、地域の防災関連団体が主催する防災イベントが各地で開催されます。
例えば、消防署や市役所の敷地で防災フェアが開かれ、そこに起震車(地震体験車)が登場して震度7の揺れを体験できたり、VR防災体験コーナーで仮想空間の災害シミュレーションを体験できたりします。
また防災資料館・防災センターの一般公開や、防災科学館での特別展示、非常食の試食会、救助犬デモンストレーションなど、楽しみながら防災を学べる催しも多彩に企画されます。
9月1日に「やっておくべきこと」(家庭・職場・地域で)
防災の日は、各自が日頃の防災対策を見直す絶好の機会です。
家庭、個人、職場、地域それぞれの場で「いざという時に備えて何をすべきか」を点検し、行動に移しましょう。
ここでは具体的なチェックポイントを紹介します。ぜひやってみてください。
【家庭】備蓄の見直し
非常食・飲料水は、一般的な家庭では最低3日分、可能なら1週間分以上の食料・飲料水を備蓄しておくことが望ましいとされています。
目安として水は1人1日あたり3リットル必要と言われています。
例えば4人家族なら3日分で36リットル、7日分では84リットルもの水が必要です。「そんなに!?」と驚く量ですが、人が生命を維持するには飲み水に加え簡単な調理や衛生にも水が必要になるからです。
さらに、非常食(アルファ米、乾パン、レトルト食品、栄養バー等)も家族人数×数日分は確保します。普段から消費・補充を繰り返す「ローリングストック法」を取り入れると、ムダなく備蓄品を管理できます。
備蓄をすでにされている方は、9月1日には賞味期限のチェックを行い、期限が近いものは日常で消費し新しいものと入れ替えてください。
家庭ごとに必要な備蓄品は異なりますが、一般に以下のようなものを準備します。
- 水・飲料:1人1日3L目安×人数×日数分(市販水、浄水器水、調理用含む)
- 主食:アルファ米、ご飯パック、クラッカー、パン缶など主食になるもの
- おかず類:レトルトカレー・スープ、缶詰(魚、肉、野菜)、フリーズドライ味噌汁等
- おやつ:チョコレート、キャンディ、ビスケット(高カロリーで保存性の高い物)
- 燃料:カセットボンベコンロとボンベ、簡易ストーブ(停電時調理用)
- 衛生用品:簡易トイレ袋、ウェットティッシュ、アルコール消毒液、生理用品など
- その他:常備薬、予備眼鏡・コンタクト、乳幼児がいる場合はミルク・おむつ、ペットがいる場合はペットフードも忘れずに。
防災の日には、家族で備蓄品を一緒に確認し、「何日分足りているか?」「賞味期限は大丈夫か?」などを話し合うとよいでしょう。備蓄は「命をつなぐ最低限のライフライン」です。
非常時にも最低3日間は自力で生活できるよう準備しておくことが大切です。
【家庭】住まいの安全チェック
大地震に備え、家の中の安全対策も見直しましょう。特に背の高い家具・家電の固定は命を守る基本です。
阪神・淡路大震災では建物内で負傷した人の約46%が家具の転倒・落下による怪我だったと言われます。9月1日には各部屋の大型家具がしっかり壁や柱に固定されているか確認しましょう。
本棚や食器棚にはL字金具やポールで転倒防止策を講じ、冷蔵庫やテレビも滑り止めマットやストッパーで移動を防ぎます。寝室では倒れてきそうな家具は配置しないか、寝る位置をずらす工夫も検討します。
次に窓ガラスの飛散防止です。
窓ガラスや照明の破損は地震時に大きな危険となるため、ガラスには飛散防止フィルムを貼っておくと安心です。特に就寝中に地震が起きるケースを考え、寝室の窓ガラス対策は重要です。
また家の中の避難経路を確保しましょう。
廊下や玄関付近に背の高い家具があると、倒れてドアを塞ぎ閉じ込められる恐れがあります。玄関や出口付近にはなるべく物を置かず、非常時にスムーズに外へ出られる導線を意識してください。
火災予防策として、感震ブレーカー(地震時に自動で電気を遮断する装置)の導入も検討してください。
感震ブレーカーとは、一定以上の揺れを感知すると電気を自動遮断する機器で、地震後の通電火災(二次火災)を防ぐのに役立ちます。分電盤に取り付けるタイプやコンセントに繋ぐ簡易タイプがあります。
設置が難しい場合も、せめて就寝前にアイロンやヒーターなど火災リスクのある電気製品の電源を切っておく習慣をつけましょう。
- 家具固定具は緩んでいないか?(金具増し締め、粘着テープ劣化確認)
- 冷蔵庫や電子レンジはストッパーで固定されているか?
- 窓ガラス・食器棚ガラスに飛散防止フィルムは貼ってあるか?
- 寝室や子供部屋のレイアウトは安全か?(頭上に落下物の恐れがない配置か)
- 感震ブレーカーまたはブレーカー自動遮断装置は設置済みか?作動確認は?
- 非常持出品(後述)は玄関近くなどすぐ持ち出せる場所にまとまっているか?
- ガス漏れ火災防止のため、ガスメーターの地震検知遮断機能を確認したか?
こうした項目を家族でチェックし、必要な対策を講じておきましょう。
「自宅=一番の避難所」です。家の安全度を高めることが何よりの防災につながります。
【家庭】家族の安否確認ルール
大災害時には家族が離れ離れになる可能性も考えて、家族間の安否確認方法や合流場所のルールを決めておきましょう。
まず緊急連絡手段として、災害用伝言ダイヤル(171)や携帯電話の災害用伝言板サービスの使い方を家族全員で共有します。
集合場所(避難場所)も決めておきます。
自宅が被災して住めない場合にどこで落ち合うか、自宅近くの避難所や実家・親戚宅など複数の合流候補地点を想定しておきます。
さらに、家族で自宅周辺のハザードマップ(洪水・津波・土砂災害などの危険エリア地図)を確認し、自宅がどんな災害リスクに晒されているか把握しましょう。
例えば「うちは洪水浸水想定エリアだから、大雨警報時は○○小学校に避難しよう」など、災害種類ごとの避難行動を事前に話し合っておくといざという時慌てずに済みます。
防災の日には家族で地図を広げ、「ここが危ない」「この道は通れるか?」などシミュレーションしてみてください。
家族の中で災害発生時の役割分担も決めておきます。
例えば「お父さんは子どもを迎えに行く」「お母さんは祖父母の誘導をする」「長男はペットをキャリーに入れる」等、それぞれ優先して担う行動を決めて共有します。
そうすることで実際の混乱時にもスムーズに動けるでしょう。
大切なのは「平時の話し合い」です。
防災の日をきっかけに家族全員でテーブルを囲み、「もし大地震が起きたら?」「夜間・外出中ならどうする?」とシミュレーションしてみましょう。
【個人携行】“いつもバッグ”の非常持出セット
大災害はいつどこで起きるか分かりません。
外出先や通勤途中で被災する可能性も考え、普段持ち歩くバッグの中に最低限の防災グッズを入れておくと安心です。
いわゆる“持ち出し用防災ポーチ”や“いつもバッグ”の準備です。
重くなりすぎない範囲で、以下のようなアイテムを常備しておきましょう。
- 懐中電灯 or 小型LEDライト:夜間停電時の照明用。小型で明るいもの。
- モバイルバッテリー:スマホ充電用。満充電にしておき、ケーブルも忘れずに。
- ホイッスル(笛):閉じ込められた時に音で救助を呼ぶため。小型で首掛けできるもの。
- 簡易トイレ:携帯用トイレパック1〜2個。長時間閉じ込められた場合に備え。
- 飲料水(500mlペットボトル):最低1本は携帯。喉の渇きや負傷時の洗浄にも。
- 携帯ラジオ:情報収集用。スマホでも代用可だがバッテリー節約のため小型ラジオがあると◎。
- 現金(小銭含む):非常時は電子マネーが使えない可能性あり。公衆電話用に10円玉も。
- 救急用品:絆創膏、消毒シート、常備薬(持病薬がある人は数日分)。
- 連絡先カード:家族や親戚の電話番号を書いたメモ。スマホ故障に備えアナログで持つ。
- 保温・雨具:アルミブランケットや折り畳み雨具。夏でも夜冷える可能性あり。
- マスク:防塵用・感染症対策用に数枚。
- ビニール袋:何かと使える。ゴミ捨て、雨避け、簡易トイレ処理など。
これらをポーチや小袋にまとめ、毎日持ち歩く通勤通学バッグに入れておきます。
市販の「携帯用防災セット」もありますが、自分に必要なものを取捨選択してカスタマイズすると良いでしょう。
ポイントは「普段から無理なく持ち歩ける重さ・サイズ」にすることです。いざという時この最小セットがあれば、初期対応で生死を分けるケースもあります。
【職場】安否確認・初動体制・BCP訓練
職場では、従業員の安全確保と事業継続のために防災計画と訓練が不可欠です。9月1日には会社の防災担当者を中心に次の点を確認・訓練しましょう。
大規模災害時に社員の安否をどう把握するか、安否確認システムや連絡網を点検します。社員連絡先リストの最新化、緊急連絡メールの訓練送信などを実施します。
社内で地震が発生した想定で、初動対応フローをシミュレーションします。
例えば「〇〇氏が非常放送で避難指示」「〇〇課長が消火班を指揮」「人事部は総務と連携し安否集約」等の役割分担を訓練します。事前に防災マニュアルや社内BCP(事業継続計画)に基づき役割を決めておき、その通り機能するかチェックします。
社屋内の避難ルートを社員全員で歩いて確認します。非常階段や非常扉の場所、避難時の注意点を共有します。
また、社員の集合場所(社外の一時避難所)や、帰宅困難になった際に会社で待機する場合の対応も周知します。会社に備蓄している非常食・飲料水、発電機、懐中電灯、救急箱などの点検も行います。
大企業では従業員数日分の備蓄を置くところもありますが、中小企業でも最低限の水・食料やヘルメット、毛布などを備えておくと良いでしょう。
【地域】自治会の連絡網・避難所開設手順・共助訓練
大災害時には公的支援が来るまでの間、近隣住民同士で助け合う「共助」が欠かせません。防災の日は自治会や町内会単位で地域防災力を見直す機会にしましょう。
自治会ごとに住民同士の緊急連絡網を整備しておきます。
班長・組長が各戸の安否を確認して取りまとめる方式や、地域の防災担当者に報告するルートなどを決め、実際に名簿や連絡ツールを準備します。
年1回は連絡網訓練を実施し、電話・メール・掲示板など適切な方法で全戸に情報が行き渡るか確認しましょう。
地域の小学校や公民館など指定避難所がスムーズに開設・運営できるよう、自治会で手順を決めます。
避難所の鍵の所在、開錠する人、照明やトイレの使用方法、受付担当者の配置などを事前にマニュアル化し、防災週間中に避難所開設訓練を行うと実効性が高まります。実際に住民有志で避難所を設営し、受付〜避難者誘導〜物資配給の模擬をすると課題が見えてきます。
地域には高齢者や障がい者、乳幼児連れの家庭など災害時要配慮者がいます。自治会では平時からそうした方々を把握し、いざという時に誰が声掛け・避難支援するか決めておきます。
「○丁目の独居高齢のAさんはお隣のBさんが様子確認」「避難所ではCさんが福祉スペース担当」等、具体的な支援分担を決めて訓練しておくと安心です。
消防や消防団と連携し、地域の初期消火訓練や救護訓練を行いましょう。消火器や消火栓の使い方訓練を町内会で企画し、実際に住民が消火器を操作する体験をします。
また応急手当講習として、止血法・心肺蘇生法(CPR)・AED使用法を学ぶ場を設けるのも有効です。地域の防災士や救急救命講習受講者が講師となり、住民同士で教え合う形にすると参加意識が高まります。
「自分たちの街は自分たちで守る」という意識の醸成が、防災の日の目標です。
自主防災会で保有する発電機、投光器、担架、無線機など資機材の動作確認もこの機会に行いましょう。倉庫の場所や鍵の管理者を周知し、いざ使おうとしたら故障していた…ということのないよう点検します。
地域ぐるみの防災活動は、普段からの顔の見える関係づくりも大切です。9月1日には防災訓練後に住民の交流会を開いたり、防災グッズ展示会を催すなどして地域の防災仲間づくりを進めるとよいでしょう。
「共助の輪」が広がれば災害への対応力は確実に高まります。
【チェックリスト】政府の備えガイドPDFを活用&自分仕様に追記
内閣府や首相官邸のウェブサイトでは、家庭の防災対策についてチェックリスト形式のPDFが公開されています。
例えば「災害への『備え』チェックリスト」には非常持ち出し袋や備蓄品の項目が網羅されており、「□水(最低3日分×1日3L)□懐中電灯□携帯ラジオ□医薬品…」といった形で自宅の備えを自己点検できます。
まずはこうした政府推奨のチェックリストを印刷するか画面で表示して、9月1日に一つ一つチェックしてみましょう。防災の日に毎年チェック&アップデートを続ければ、徐々に「我が家の防災力」が高まっていくはずです。
コラム:なぜ“二百十日”は警戒日なの?
9月1日前後の話題として登場する「二百十日(にひゃくとおか)」について、少し掘り下げてみます。
雑節としての意味と農事暦での位置づけ
二百十日は: 二百十日は雑節(ざっせつ)の一つで、立春(2月4日頃)から数えて210日目の日を指します。
新暦では毎年だいたい9月1日頃に当たり、昔から台風襲来の厄日とされてきました。
江戸時代以降の農村暦では八朔(8月1日)、二百十日、二百二十日が「三大厄日」と称され、稲作に被害をもたらす暴風の日として警戒したのです。
農業と台風の関係: ちょうど二百十日の頃は稲の開花期(穂が出て花が咲く時期)にあたります。
この時期に台風で強風や豪雨に見舞われると、稲穂が倒れたり実りが損なわれてしまうため、農民にとって非常に恐ろしいタイミングでした。
そのため「二百十日は台風が来やすい」という言い伝えが生まれ、各地で風祭(かぜまつり)など台風封じの祈祷が行われたりしました。
具体的には「二百十日に鎮守様にお参りすると台風避けになる」等の風習も残っています。
実際の気象データ: しかし現代の気象統計によれば、必ずしも二百十日前後に台風が襲来するわけではありません。
台風のピークシーズンは8月後半から9月にかけてですが、その年ごとに時期はばらつきます。
むしろ二百十日は「これから秋の台風シーズンに入る」という目印の日と考えるのが適切でしょう。
実際、戦後日本において9月1日(=二百十日頃)に台風が上陸した例は、1949年のキティ台風のみというデータがあります。
このことから、防災の観点では二百十日そのものより、その前後を含む立春後210〜220日目あたりは警戒期間と心得るのが良いでしょう。
データが示す特異日:9/16・9/26に集中?
興味深いことに、気象データを分析すると台風襲来の「特異日」が浮かび上がります。
それが9月16日と9月26日です。
過去の大型台風で被害が大きかったものの上陸日を見ると、この両日に集中しているケースが多いのです。
9月16日襲来: 代表例はアイオン台風(昭和23年=1948年9月16日)と第2室戸台風(昭和36年=1961年9月16日)です。
アイオン台風は関東・東北に被害を与え、第二室戸台風は高知県室戸岬付近に上陸して近畿地方に甚大な被害をもたらしました。
奇しくも同じ9月16日に強烈な台風が襲ったことから、この日付は統計上注意日と指摘されます。
9月26日襲来: さらに顕著なのが9月26日です。
【昭和29年(1954年)の洞爺丸台風】、【昭和33年(1958年)の狩野川台風】、そして前述の【昭和34年(1959年)の伊勢湾台風】が、いずれも9月26日に日本に上陸し甚大な被害を出しています。
特に伊勢湾台風は戦後最大の台風災害であり、この出来事が9月26日という日付を強烈に印象付けました。
これほど9/26に集中するのは偶然の面もありますが、9月下旬は台風の勢力が衰えにくく進路も本州に向かいやすい時期であることが背景にあります。
そのため気象関係者の間では「9月後半は要警戒」という教訓が共有されています。
ただし、あくまで統計的な話であり、近年では10月に大型台風が来るケース(2019年台風19号など)も増えています。
したがって結論的には、「二百十日(9/1頃)」は象徴的な警戒日、実際には9月中旬〜下旬の台風来襲リスクが高いと理解しておくと良いでしょう。
防災の日がこの時期に定められたのも、そうした伝統的戒めと近代の災害教訓を合わせて想起させる意味があるのです。
古来からの知恵と現代のデータ、両方に学びつつ備える姿勢が求められています。
いま改めて「防災の日」が注目される理由
最後に、2020年代の現在において「防災の日」が改めて注目される理由について考えてみましょう。
背景には、過去の教訓の風化を防ぐと同時に、差し迫った新たな巨大災害のリスクへの備えを強化する必要性があります。
関東大震災の教訓と現代の巨大地震リスク
2023年で関東大震災からちょうど100年という大きな節目を迎えました。
災害から1世紀が経ち、当時を直接知る人がいなくなる中で、その教訓をどう現代に伝え減災に活かすかが問われています。
関東大震災の悲劇と教訓(例えば「火災の恐ろしさ」等)を現代社会にアップデートして語り継ぐ動きが活発化しており、防災の日にも各種メディアやイベントでこれらが発信されました。
特に「災害教訓は次の大災害までの命綱」との思いから、100年目の今、防災の日が改めてクローズアップされています。
一方で、現代日本は新たな巨大地震の脅威に直面しています。専門家によれば、今後30年以内に首都直下型のM7クラス地震が発生する確率は70%程度とも予測されています。
また西日本の太平洋沖ではマグニチュード8〜9規模の南海トラフ巨大地震が30年以内に70〜80%の確率で起こるとされています。
これらは明日起きても不思議ではない高リスク事象です。
発生すれば東京圏では最悪2万3千人の犠牲、南海トラフでは32万人超の犠牲も想定され、その被害額は東日本大震災を遥かに超えると試算されています。こうした現実に迫る巨大災害リスクに対し、一人ひとりの備えを急がねばならないとの危機感が高まっています。
そこで防災の日が果たす役割が再評価されています。
100年前の関東大震災から得た教訓(避難の重要性、デマの危険、都市インフラ脆弱性など)をもう一度学び直し、来るべき首都直下地震や南海トラフ地震への備えに活かす。
それこそ防災の日の原点に立ち返る意義でしょう。
「あの日」の悲劇を無駄にしないために、「今日」自分たちが何をすべきかを考える日として、防災の日が改めて注目を集めています。
“知識→体験→行動”で減災へ
現代はネットやSNSで災害情報・対策が容易に手に入ります。しかし、頭で知っているだけでは実際の災害時に適切に行動できないこともあります。
防災は「知識→体験→行動」のサイクルを経て初めて身につくものです。どんなに本や動画で知識を得ても、それを実際に体験・訓練しておかないと緊急時には身体が動きません。
まさに「頭で理解しただけでは行動に結びつかない。訓練でできないことは本番でもできない!」という言葉に尽きます。
防災の日・防災週間は「知識を体験に移す機会」として重要視されています。各種防災訓練に参加し、避難行動や救急措置を実際にやってみることで、初めて自分の行動として身につきます。
日本では毎年どこかで地震や台風、水害が発生し、そのたびに一時的に防災意識が高まります。しかし時間とともに危機感は薄れ、また備えがおろそかになる傾向があります。
防災の日という定期的な節目があることで、「そうだ、非常食をチェックしよう」「今年こそ家具固定をしよう」と人々の行動をリマインドし変容させる効果が期待できます。
特に近年は気候変動の影響で豪雨災害も頻発しており、他人事ではないとの認識が広がっています。だからこそ9月1日を契機に、各個人・各家庭が具体的な防災アクションを起こすことが大切です。
まとめ
「防災の日」は過去の犠牲者への鎮魂と教訓の継承の日であると同時に、未来の命を守る行動を起こす日でもあります。
毎年9月1日が巡ってくるたび、私たちは立ち止まって備えを見直し、「その日」が来ても最善を尽くせる自分であるかを問い直さねばなりません。
災害大国・日本に生きる以上、防災は生活の一部です。
ぜひこの機会に、防災知識を行動に移し、日々の暮らしに減災の工夫を取り入れてください。
そして「今日できる備えは今日のうちに」実践し、次の世代にも語り継いでいきましょう。
それこそが防災の日の本当の意義と言えるのではないでしょうか。